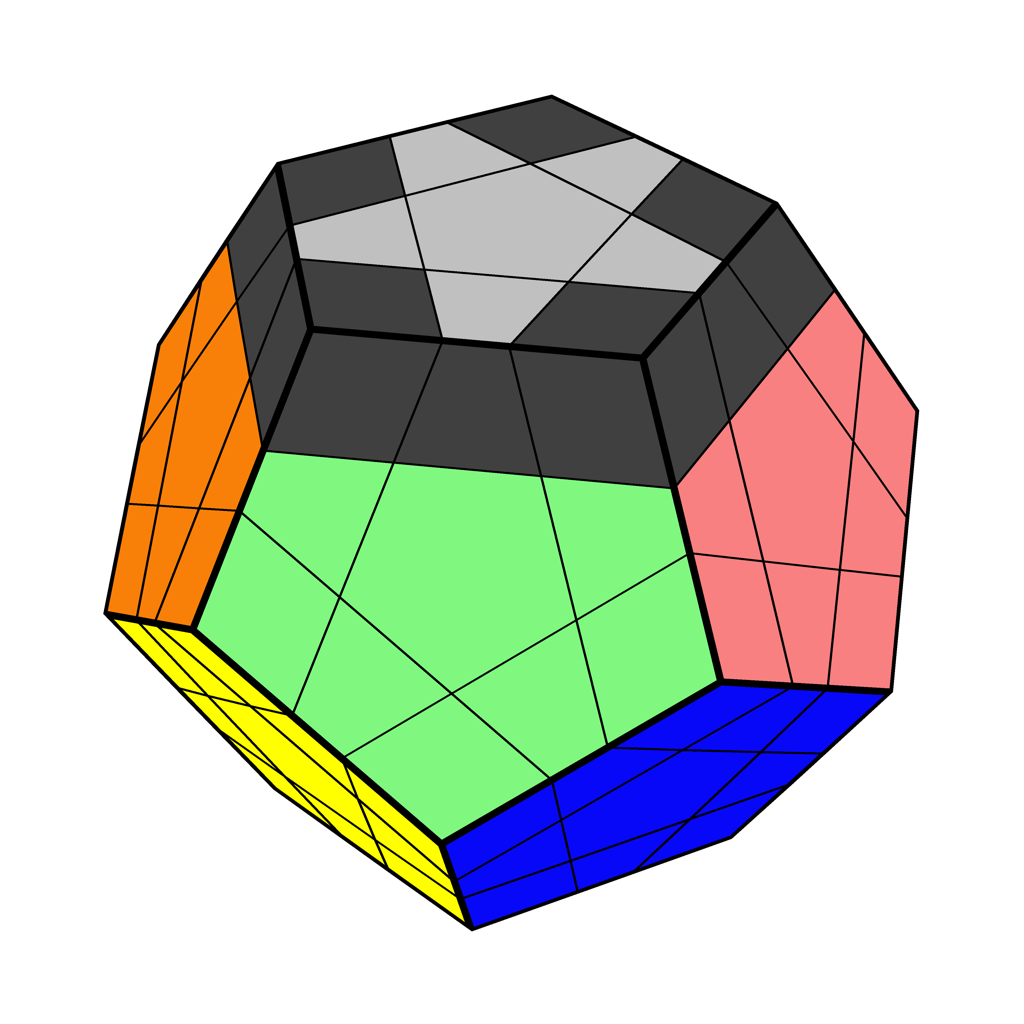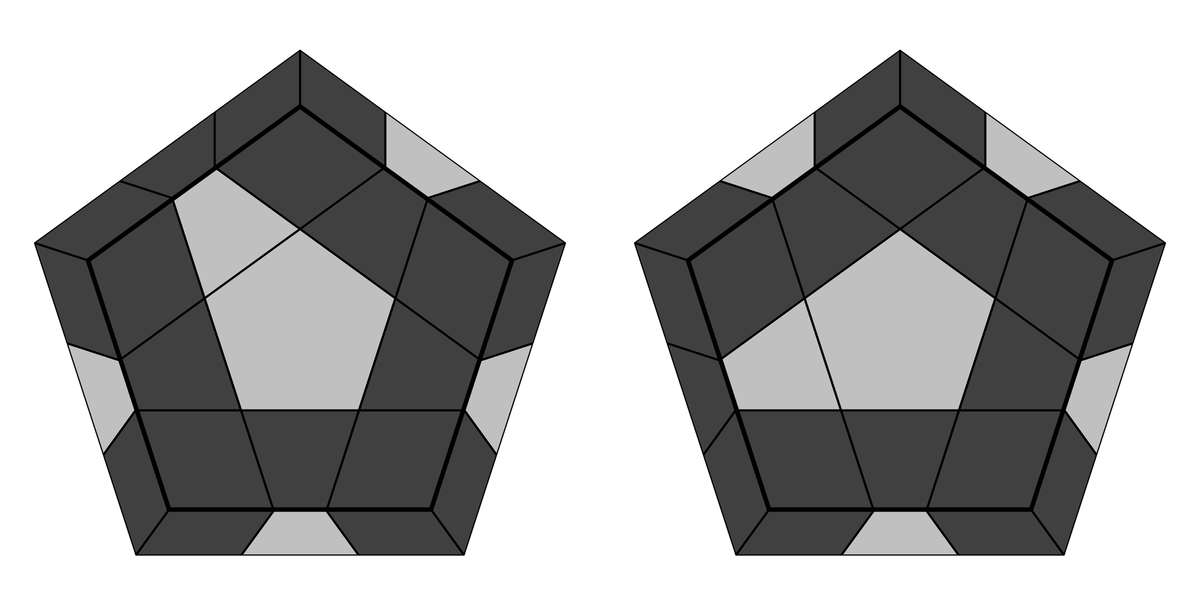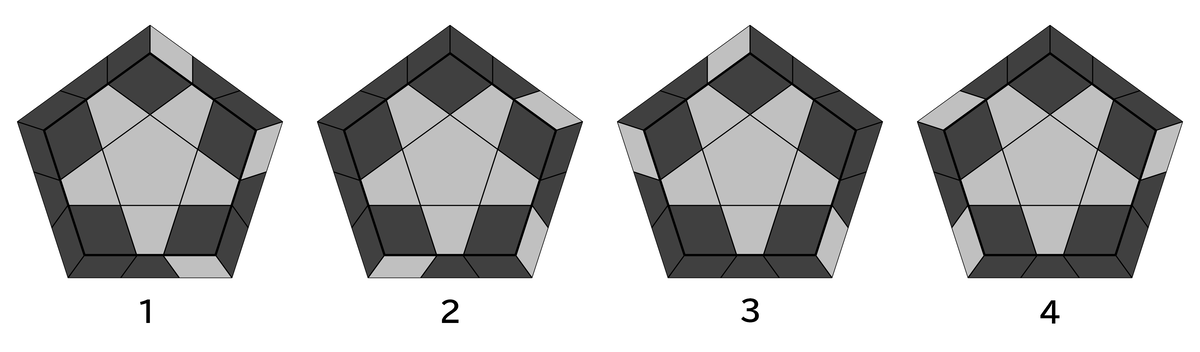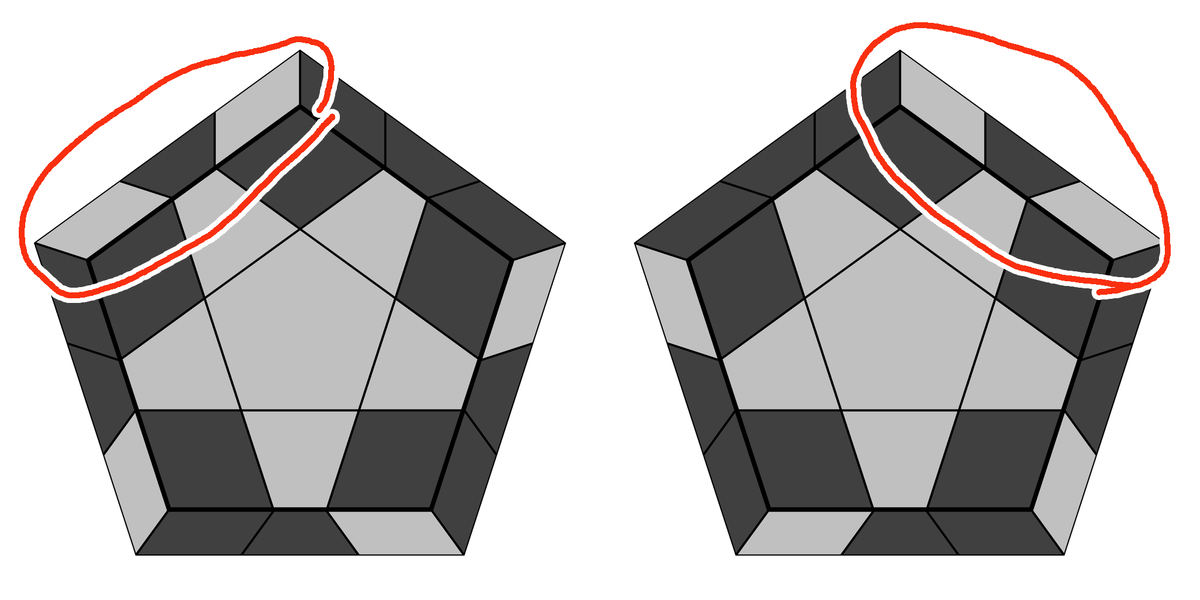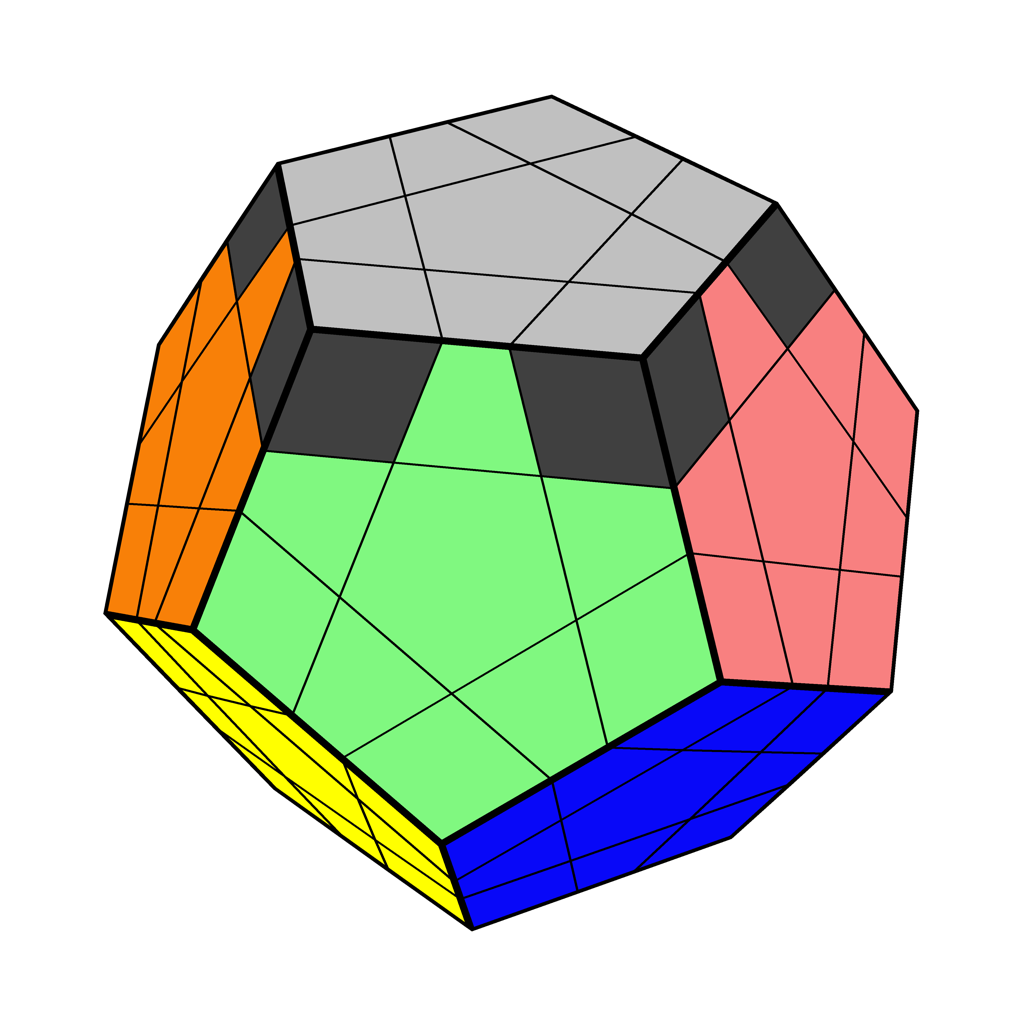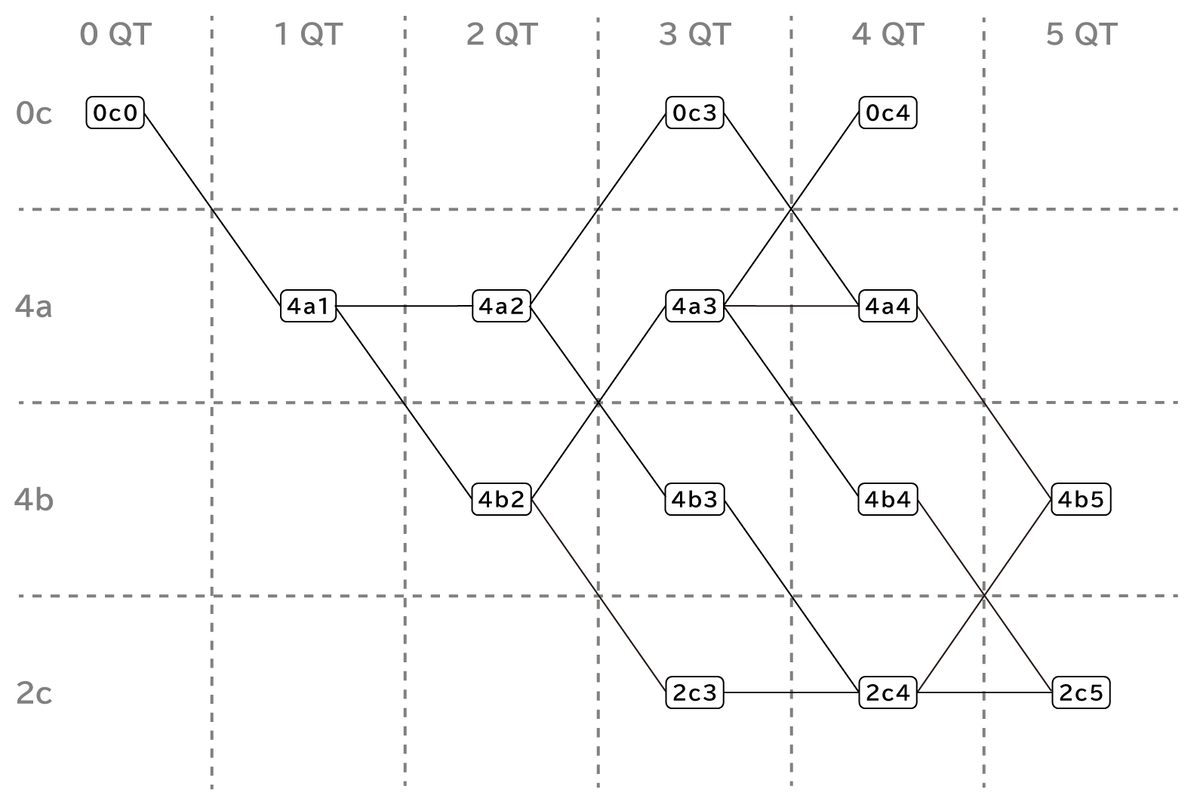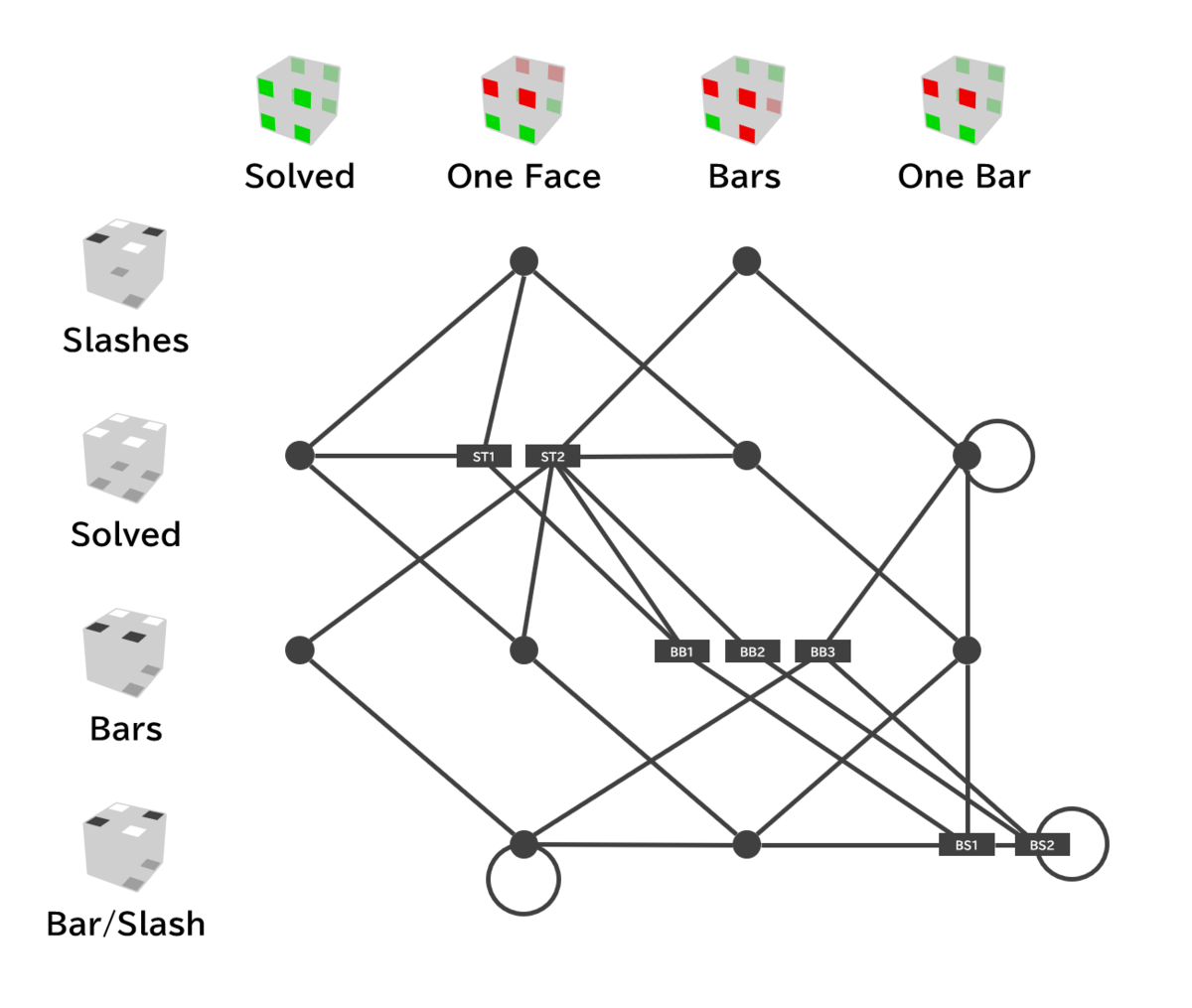www.worldcubeassociation.org
Fewest Moves Challenge、最少手数競技。「ルービックキューブで世界新記録!」みたいなのはいかに速く解けるかを競っているが、この競技はいかに短い手数で解けるかを競う。
お題が与えられ、1時間の時間制限の中で、紙とペンとキューブを使って、なるべく短く解く手順を見つけて提出する。
これを3回やって、平均が一番短い人が勝ち。
3x3x3キューブはどんな状態からでも20手で解けるということが知られているが、20手掛かる状態というのはとてもレアで、ランダムに生成したら0.000000001%くらいの確率でしか出てこない。だいたいは18手か17手、数%くらいで16手か19手という感じ。
www.cube20.org
トップの人は人力でこの真の最短解+数手の解を人力で見つけるからすごい。
ちなみに、普通にキューブを解くとだいたい60手くらいになる。
解き方は普通にキューブを解くのとは全く異なる。
どんな解き方をしているのかはこの辺を見ると良い。
kawam1123.github.io
note.com
1個目のほうは全体的にまとまっているが、解法が古い。
1個目の「付録D: ドミノリダクション入門」の解法が2025年現在の主流。
要は各ステップで色々と試行錯誤をする。
その中でときどきそのステップの短い手順が出てくる。
ガチャのように射幸心が煽られて楽しい。
宣伝
このFMCの同人誌を、2024年の冬コミで頒布した。
sanya.sweetduet.info
とらのあなに販売委託していたけれど、すでに終了してしまっている。
そのうち在庫が送り返されてくるらしい。
5月末からの技術書典18でも頒布する予定なので、よろしくお願いします。
イベント自体が通販もやっているので、ネットでも買える。
techbookfest.org
あと、このFMCの各ステップをコンピューターで解くツールも作ったので使ってほしい。
目標
平均30手未満。
こんなことを言っていて、まさか3か月後にまたFMCの大会があるとは思わなかった。
持ち物
スマートウォッチではない腕時計があると良い。
試験みたいなものなので、電子機器は使用不可。
前に時計は置かれていたけれど、やはり手元で見たい。
あと、キューブによってはセンターキャップを外す器具。
「キューブをチェックします。センターキャップを外して見せてください」と言われた。
Bluetoothでスマホと繋がるキューブがあるので、そういうものではないか確認すると。
最近のGANのキューブは専用の器具が無いと外せない。
「この競技でキューブのメンテをしたくなることないだろ。でも、まあ、一応持っていくか」と持っていっていて良かった。
第1ラウンド第1試技
スクランブル。
R' U' F U2 R2 F R2 D2 U2 B R2 B' L U B' F R D' R2 B U2 L2 F R' U' F
4手EOが1個も無い。
なんだこのスクランブル……。
出鼻がくじかれる。
……と、本番中は思っていたけれど、今ソルバーに掛けたら4手EOが3個あったわ。
- L (F2 B R)
- D (B' R' D)
- (R' D) L' D
3個目の2+2手のものは仕方が無いにしても、1個目と2個目は見つけられても良かった……というかこの形のものはチェックしていたはずだけど……。
見落としていたらしい。
こういうことを大会が終わった今やっていてももう遅く、大会前の練習のときから、解いた後にツールを使って見落としが無いかチェックしておくべきだった。
反省。
見つけたDRは、15手2c5、14手2c4、14手2c4、17手2c4。
このステップも今ひとつ。
まあ、選ぶなら14手2c4だろうな。
HTRまではHT(Half Turn、180度回転)ほぼ最少でいけて悪くない。
HTR以降もすんなりleave sliceにいけて、VR状態だった。
VRの話は↓。スライスインサートが機械的にできて良い。
note.com
スライスインサートで+1手で31手。
良くはないけど、まあスクランブルの運も悪いだろうし、「あれ、書いた手順で揃わない? なんで???」みたいに慌てることもなく、時間に余裕を持って何度かチェックもできたし、良い感じ。
B L R2 D' F' // EO (F/B) (5/5)
// DR-4e4c (R/L) (0/5)
R D2 F2 R' F2 R U2 R' U // DR (R/L, 2c4) (9/14)
B2 R F2 R' F2 R F2 R * // HTR (8/22)
B2 U2 R2 * // FR (R/L) (3/25)
B2 U2 B2 D2 F2 // LS (R/L, VR) (5/30)
* = E2 // finish (1/31)
B L R2 D' F' R D2 F2 R' F2
R U2 R' U B2 R F2 R' F2 R
F2 R' L2 F2 D2 L2 B2 U2 B2 D2
F2
第1ラウンド第2試技
スクランブル。
R' U' F D' B2 L2 B U R' D' L' U2 F2 R B2 D2 L B2 L B2 L F2 B' R' U' F
見つけたDRは、16手4b3or4、16手4a2、16手2b5、16手2c4。
だめだこりゃ。
だめだし、DR探索をねばって時間が無くなってしまったのが良くない。
結局2個目に見つけた16手4a2を選択し、HTRを探索する時間が無くて、ほぼそのまま解いただけ。
36手。
つらい。
(F L R2 B) // EO (F/B) (4/4)
(R U) // DR-4e4c (R/L) (2/6)
(L B2 L' U2 R' U2 R U2 L U) // DR (R/L, 4a2) (10/16)
R2 B2 R * D2 R2 F2 D2 B2 D2 B2 D2 B2 R' * // HTR (13/29)
B2 R2 B2 D2 R2 + // FR (R/L) (5/34)
D2 U2 // LS (R/L) (2-1/35)
* = M', + = M2 // finish (1/36)
R2 B2 L B2 R2 D2 B2 U2 B2 U2
B2 U2 R2 L F2 R2 F2 U2 L2 D2
U L' U2 R' U2 R U2 L B2 L'
U' R' B' R2 L' F'
第1ラウンド第3試技
スクランブル。
R' U' F L2 D' B2 R2 B2 F2 U F2 U' F R F2 D' R B2 L2 D R F R' U' F
疲れているのか運が悪いのか分からないけど、RZP(DR-XeXc)からのDRが、手数が長くなりそうなものばかり。
17手4a3と19手4a3を見つけただけ。
17手4a3からのleave sliceが35手。
まあ、しょうがないか……とスライスインサートをしたけど、なんか揃わない。
やばい。
結局、書いた手順を間違えていたわけではなく、手順を回すときに間違えていたっぽい。
もう時間が無いから、スライスインサートではなく、普通にスライスを揃えた。
41手。
DNFにならなかっただけマシか。
基本的には平均で競うので、DNFが1個でもあると、その時点で最下位になってしまう(DNFがある人同士の中では、DNF以外のベストの記録で順位が付く)。
(R) U F' B2 R' // EO (R/L) (5/5)
F' D // DR-4e4c (F/B) (2/7)
U2 L2 B2 R2 F U2 F' R2 B2 D // DR (F/B, 4a3) (10/17)
F L2 F2 D2 F' D2 L2 U2 L2 B' // HTR (10/27)
U2 F2 R2 U2 F2 // FR (F/B) (5/32)
R2 D2 L2 // LS (F/B) (3/35)
U2 F2 B2 D2 F2 B2 // finish (6/41)
U F' B2 R' F' D U2 L2 B2 R2
F U2 F' R2 B2 D F L2 F2 D2
F' D2 L2 U2 L2 B' U2 F2 R2 U2
F2 R2 D2 L2 U2 F2 B2 D2 F2 B2
R'
決勝進出
31手、36手、41手で平均36手。
これは決勝進出無理かなぁと思ったけど、通っていた。
良かった。
単発記録も平均記録も自己ベストを更新できていないので、これで終わりは悲しい。
決勝進出ラインは、ほぼ、DNF無しで平均記録を残せたかどうかだった。
「皆、キューブを普通に解くことはできるんでしょ? DNFにしないだけなら簡単では?」と思われるかもしれないけど、これが意外と難しい。
特に焦っていると、書いた手順を回してみても揃わなくてどうしようもなくなる。
やってみると分かる。
なお、決勝進出は上位75% それなら単に全員2ラウンドで良くない? と思うかもしれないけど、これが主催者の裁量で可能な上限。
ラウンド数などは主催者が好き勝手にできるわけではなく、WCAの定めるレギュレーションがある。
例えば、競技者が100人未満だったら4ラウンド制にすることはできない。
その中に各ラウンドでは少なくとも25%の競技者を除外しないといけないというルールがある。
www.worldcubeassociation.org
1回の大会で良い順位を取ることよりも、記録を残すことを目的にする人は多い。
そういう競技者にとっては「この大会は10ラウンド制! 全員次のラウンドに行けます! 要は10回挑戦できます!!!」みたいな大会があると嬉しいし、そういう大会も開かれるだろう。
でも、そんな何回も挑戦して出した記録で「世界新記録です!」というのは違うのでは? ということなのではなかろうか。
決勝第1試技
スクランブル。
R' U' F U2 R2 F R2 D2 U2 B R2 B' L U B' F R D' R2 B U2 L2 F R' U' F
4手EOがそのままDR-4e4cになっていて、それが簡単にDRにできて9手4b2。
決勝進出者へのご褒美感ある。
これ、大会の記録での自己ベストどころか、家での練習も含めても自己ベスト狙えるのでは? と思ったけど、FR以降は今いちだった。
25手。
まあ、充分でしょう。
(F L' D2 B') // EO (F/B) (4/4)
// DR-4e4c (U/D) (0/4)
(L2 U' B2 D L') // DR (U/D, 4b2,6e) (5/9)
(U2 B2 U' * F2 D') // HTR (5/14)
(R2 U2 * B2 L2 B2 R2 B2 R2 U2) // FR (U/D) (9/23)
(L2) // LS (U/D, VR) (1/24)
* = E2 // finish (1/25)
L2 U2 R2 B2 R2 B2 L2 B2 D2 L2
D B2 U' D2 B2 U2 L D' B2 U
L2 B D2 L F'
終わった後に聞き耳を立てていたら「9手4b2が~」という話があちこちから聞こえてきた。
決勝第2試技
スクランブル。
R' U' F L2 B' F' U2 F' U2 L2 F U' F D U' R2 F R' U R' U F2 R' U' F
見つけたDRで一番良いのが11手2c4。
そこから29手。
良くも悪くもなくというか、実力通りというか、これがコンスタントにできればとりあえず満足感がある。
D R U // EO (U/D) (3/3)
L F // DR-4e4c (R/L) (2/5)
D2 R' L U2 R F // DR (R/L, 2c4) (6/11)
(R D2 R' %) R2 B2 U2 R' * U2 R + // HTR (9/20)
U2 F2 U2 R2 // FR (R/L) (4/24)
F2 B2 D2 B2 // LS (R/L) (4/28)
* = M2, + = M', % = M // finish (1/29)
D R U L F D2 R' L U2 R
F R2 B2 U2 R L2 D2 L B2 U2
B2 R2 U2 D2 F2 D2 L D2 R'
決勝第3試技
R' U' F R2 D' L2 D2 R2 U' B2 U' F2 L D' F L' F' U' R2 U2 L U R' U' F
11手4a3or4、10手2c4、11手2c4、13手2c5。
悪くはないけど……と思っていたらDR探索の最後のほうで9手4b2を見つけた。
ラッキー。
そこから29手とか27手とかになっていたけど、スイッチしてみたら、14手HTRからの24手leave slice。
第1試技の記録を更新できるのでは? と期待したが、スライスインサートが+2手だった。
VRを使い始めて以来、初めてこのパターンを見た。
解答を書き下して、DR以降を末尾に移動するとこうなる。
U2 U2 D U'
B2 R2 R2 F2 L2 F2 L2 B2 F2 R2
簡略化。
F2 R2 || F2 || F2 | F2 R2 |
+0手で反転できるのが最後の区間しかなく、反転するとVR化する。
これと、 E2 を挿入したときの影響は次の通り。
U2 U2 D U'
B2 R2 R2 F2 L2 F2 L2 B2 F2 R2
E E
f g f g
エッジは完成状態でセンターが反転しているので、和がdotになるように奇数回の E2 を挿入する必要がある。
r があれば、 r+f+g=t でいけるけど、無いので無理。
U2 U2 D U'
B2 R2 R2 F2 L2 F2 L2 B2 F2 R2
E E
f r g f r g f r g
E2 E2 E2
こうして+2手。
今にして思うと、+1手でVR化し、その後+0手で完成させられる可能性はあったか。
とはいえ、ソルバーに掛けてみても+2手しか無かった。
(U2 R' F) // EO (F/B) (3/3)
U R // DR-4e4c (U/D) (2/5)
D L2 U' L // DR (U/D, 4b2) (4/9)
(U * R2 F2 D' *) // HTR (4/13)
(B2 U2 * L2 F2 L2 F2 R2 * U2 *) // FR (U/D) (8/21)
(L2 B2 R2) // LS (U/D) (3/24)
* = E2, + = E' // finish (2/26)
U R D L2 U' L R2 B2 L2 D2
L2 U2 D2 F2 L2 F2 L2 D2 F2 U
R2 B2 D' F' R U2
まとめ
予選は全然だめだったが、決勝は普段より上振れた感があって良かった。
今後。
まずは正確性を上げることか。
いちいち書かなかったが、わりと良くできた決勝でも「あれ、揃わない。おかしいな」ということは度々あった。
私より上の人達、私が「今回はすごくラッキーだった」という手数が、「最悪でもこのくらいは」という手数である。
どうすればそうなれるかというと、探索の物量っぽい。
たぶん、私の10倍くらいの量を探索している。
あと5手くらいというと小さく思えるが、そもそも真の最短解よりは縮まず、真の最短解+4手くらいと真の最短解+9手くらいと考えると差は大きい。
1手縮めるのに倍くらいの探索量が必要なのではという感覚がある。
しかし……「FMCはスピード競技と違ってじっくり考えられるから良いね」と思っていたが、1周回ってスピード競技に戻ってきた感が……。
おまけ
大会の翌日にこの記事を書いている。
昨日は1時間×6回=6時間の試技をした。
大会に出るような人でも、1日6回も練習をすることはまず無いらしい。
で、6時間机に齧り付いているとどうなるか? 今、筋肉痛で首と肩が痛い。
動かなくても筋肉痛になるんだ……。
体力も重要なのかもしれない。